
* 縦書きのものをそのままhtmlファイルに変換しています 文責 駿馬
四、第一詩集『世界の一人』出版
(三)、早稲田大学卒業
大正二年(1913)、早稲田大学卒業の年である。省吾はこの年より、徹底した口語自由詩へと傾斜してゆくべく、独自の詩論を模索しはじめている。まずは「白鳥省吾年譜」よりこの年の記事を紹介する。
<一月、詩を『劇と詩』。三月、散文詩を「讀賣新聞」。四月、散文詩「早稲田文学」。十月、評論「詩と生命の表現」「讀賣新聞」。三月三十日に「劇と詩」の会あり、山村暮鳥に初めて会う。六月早稲田大学英文科卒業。卒業論文は「エドガー・アランポーの研究」。同窓に谷崎精二、広津和郎、原田実、増田綱の諸氏。八月福島県海岸の新地、勿来方面を旅行、盆踊りを初めて見、民謡に興味を持つ。>
この中で山村暮鳥に会ったのがこの年初めてと書いているが、「大正初期詩壇漫談一」と『文人今昔』に記載した年が合わない。「大正初期詩壇漫談一」の方が古い資料であるが、手元の資料からは特定できない(前掲)。卒業論文が「エドガー・アランポーの研究」であるが、これは後の民衆派詩人としての白鳥省吾像からは想像も出来ないが、それには以下のような事情があった。大泉書店版の「ホイットマン詩集」まえがきより抜粋して紹介する。
<私は大正二年に早稲田の英文科を出るときの卒業論文はホイットマンとポーといずれにしようかと考えたのであるが、ホイットマンに就いては当時は参考書も手元に乏しかったので、ポーの方を選んだのである。>
ポーについては『詩の創作と鑑賞』の中の「第四編泰西詩壇」に於いて「ポーとボォドレールの悪魔主義」という一項目をもうけている。その中で興味深いのは、<ポーとホイットマン。それからボォドレールとヴェルハァレン、この二人宛の相対は影と日向のような印象を与える。中略・ホイットマンやヴェルハァレンの詩が吾等を勇気づけるように、ポーやボォドレールの詩は吾等の霊をうるおし純真にするものである。>と記していることである。省吾がホイットマンを知ったのが早稲田に入学した年、明治四十二年と「白鳥省吾年譜」にあるから、かなり早くから知っていたにもかかわらず、卒論はポーを選んだ。この辺の事情が、後に「民衆派には一番遅れて参加した」と言われるようになった原因と思われる。
省吾が卒業前後にどのようなことを考えていたかを、故乙骨明夫氏の「白鳥省吾論」、『詩に徹する道』より推論してみたい。
「詩の内部生命」(『劇と詩』1913.3)、「散文詩の要求」(『秀才文壇』1913.3)、「詩と象徴について」(『現代詩文』1913.11)、「詩と生命意識」(「讀賣新聞」1913.12.5-6)。『詩に徹する道』中の「覚え書き」には以下の二つがある。「象徴詩の本質」(『現代詩文』1913.10)、「詩と生命の表現」(「讀賣新聞」1913.10)。
これらの論稿を読んでみると、省吾がこれまで歩んできた詩の道の一応のまとめとみることができると思われる。また、これらの論稿は省吾が民衆派詩人へと傾斜していく過程の、詩に対する考え方を解する材料となるものとも思われるので、抜粋して紹介する。
「詩の内部生命」/私は今まで、私の詩の内容の多量を日常の生活の実感の感激の強かった「気分」を歌うことに甘んじてきた。/驚きの少ない安らかな気分詩には、深い満足を味わうことが不可能である。/詩に於いても他の芸術と均しく絶対に現代の日常使用される言葉を持って自由に表現することを浴する。/私の求むる詩と、現在の詩壇の持てる詩とは遠い距離と多少の欠陥を見出す。/淡しい平面的の滑らかな象徴と気分にもあきたらなく外面的に散文の味に堕した社会の批評、自我の心持ちを表そうとしたデレッタントの詩をも、これからの真の詩とは思わない。/
「散文詩の要求」/私、一個人より言えば私の要求するものは詩より発足した散文詩である。/内容は極めて自由なものであって其れが無意識に詩のリズムとトーンの微妙さによって包まれているものを浴する。/詩はもっと自由に或る時は純化されずに自己を盛らんとするものである。/詩がバイオリンの味わいである時、散文詩はオーケストラのようなものである。/詩人の散文詩には鋭い思想の蒸留と音楽的要素とがある。/
「象徴詩の本質」/生活と芸術との密接と言うことは、驚くべき想像力、微妙なる感覚、異常なる芸術的恍惚を排して、普通人の心境に引き下ろすことではない。/何よりも先ず自己の生命の存在に驚き、生命力の神秘と微妙を感ずることが第一である。芸術の鍵はこの驚異である。/「叙述するな、暗示せよ」とはヴェルレーヌなどの信条であり、私も亦、幻像と神秘を尊むべき現実として極度まで愛し、詩の暗示をも認める。/感覚や象徴は曖昧になりがちなものだけに、「詩的」という一種の淡しい空想的な、人生に直接交渉の薄い連想を人に惹き起こさせる。/自分を離して見、宇宙の一つの存在、永遠の一つの点として見て、始めて真の驚異が脈々と湧いてくる。/自己を客観して残忍熱列の心持ちで眺めやり、しみじみと存在の驚異を感じ、力に充ちた心で、生命力の微妙と恍惚を極所まで徹せしめようとする努力から真の詩が生まれてくる。そしていかに科学的文明が発達した人々の頭脳が散文的になるとも、優れた詩の源はこの象徴主義にあるであろう。/
「詩と生命の表現」/現今のわが詩壇は、官能と情緒、いずれの方面からしても、人間としての深く広い生命力を、遺憾なく表現し得たものとは言えない。/一般の人は詩に対して、表面的の美の憧憬、淡しいセンチメンタルな感動を表したものと言う考え方から幾歩も出ていないようだ。詩的という言葉は、空想的な、人生に直接交渉の薄いものという連想を伴っている。事実今の詩はそういう意味の「詩的」という味わいが多分に混入している。新しい詩は真に生命を意識したところから起こって来ねばならない。/今の詩は真の詩までの経路であって、真の詩ではないと言うような気がする。 /例えば地に立って居て足下がむづ痒いような神秘、慟哭したいような悲痛な心持ち、躍り上がりたいような歓喜、それを誠に常に味わい得る人で始めて力強い感動がある。宇宙の一つの点として驚異の閃光を感じ得たものと言い得る。/
「詩の内部生命」では乙骨明夫氏がその論文中で指摘しているように、これまでの詩が『自然と印象』の気分詩の傾向にあったのを反省しているように、読みとれる。
「散文詩の要求」はこの時期の省吾の散文詩に対する考え方を述べているだけで、この論自体が未だ漠然としている。しかしこれが、大正七年一月に『詩歌』に発表した「詩と散文詩」になると、
<詩の形式を破壊して散文詩になるのでない、散文詩で最も妥当に表白できる詩の内容である。詩はどんなに自由になっても、詩は詩として存在する。又、散文詩は散文詩として別に存在する。二つの平行して存在すべきものである。>
として、詩と散文詩をはっきりと区別する考えを述べている。更に大正八年八月に『短歌雑誌』に発表した「散文詩の要素」にはその要素として具体的に三つを揚げている<一,詩のリズムを有すること。二,一つの焦点を有すること。三,余り長からぬこと。以上の三つの要素の孰れかを欠いたものは、散文詩といふ分類の中に這入らないと思う。この私の見地からして、これまでの泰西の作家中、散文詩を遺した人は、ポーとボォドレールとツルゲーネフの三人である。後略>
余談になるが、この「散文詩」という考え方に対して萩原朔太郎は『日本詩人』第六巻第六号(大正十五年六月号)所載の「玉転がし」に於いて、以下のように記している。抜粋して紹介する。
<自分の人生観や社会観をまとめるために、数年前から一種の短編散文を書き付けている。それは私が「情調哲学」と呼んでいるもので、その初期の分は既に単行本となって刊行されている。爾後の分も時々雑誌で発表し、本誌にもいつか一部分を掲載した。中略・私のこの表現は、多数の短い断章を組み建てて、一つの立体的な思想を構築しようとするのであるから、一部分切り離したのでは完全ではない。中略・それでこの断片的散文は、時々の気分によって種種のスタイルで書かれている。中略・中には情趣の濃やかな象徴風のものもある。この中、比較的認識から離れていて、気分や情操を主にしたものは、世の所謂「散文詩」という型に適合する如く思われる。
散文詩ならば確かに詩の領域に属するから、詩の雑誌たる日本詩人に出しても悪くわなかろう。中略・遠慮するわけは、本来私には「散文詩」という観念の意味がはっきり解って居ないからだ。散文詩と評論とどこがちがうか?散文詩と感想とどこがちがうか?そもそもまた散文詩と普通の散文とを、何の標準よって区別するのか?(白鳥省吾君の散文詩論も、私にははなはだ不徹底に思われる。)
だから出来るならば、散文詩というような言葉を使いたくない。ただ一種の短編散文として、広義の詩の中に入れてもらへば結構だ。後略>
この両者の「散文詩」或いは「詩」のとらえ方は岩成達也氏の『私の詩論大全』に詳しい。省吾は翌大正三年に処女詩集『世界の一人』を出版するのであるが、この中に散文詩を十八編も載せている。
「象徴詩の本質」は省吾のこの時期の詩に対する考え方がよく表れていると思われる。これまでの象徴性では淡しい、もっと力強い「驚異」より発した象徴主義でなければならない、そこから真の詩が生まれると説いている。
「詩と生命の表現」は「象徴詩の本質」の延長線上に位置するものと考えられ、「驚異」がより具体的になっている。省吾はこれらの論文を発表しながら、新しい詩の方向を模索していたのであった。その目指したものは、「口語の自由詩と言う形式の象徴性を盛った詩」ということになろうか。特に、「象徴詩の本質」を読むと、省吾が象徴詩を目指しているように受け取れる。しかし、後において決して象徴詩人ではなかった。
省吾はこの中で、いささかエスカレートしたかのように、三木露風の詩集「白き手の猟人」(大正二年九月・東雲堂発行)を「露風氏の詩は、生命を掴んでの其の生命の香気や沈黙や神秘でなく、奥深い生命の周囲を彷徨っている感があるし、」と評し、続いて北原白秋の『東京景物詩』(大正二年七月・東雲堂発行)を「生命の意識が甚だ希薄なものと言わざるを得ない。」と批判している。
省吾は一貫して「驚異」を力説しているのであるが、この「驚異」は前年の大正元年六月に『劇と詩』に発表した評論「驚異より」に引き続いているものと思われる。それは<生命の神秘と生きているという深い実感から来る「生命の驚異」、自分という人間はこの全宇宙にたった一人しか生きていないという「存在の驚異」>を言っているものと思われる。こうした考えは当時の詩壇の象徴主義、自然主義、神秘主義の影響より生じたものと思われる。省吾はこの「驚異」の延長線上に処女詩集『世界の一人』を出版する事になるのであった。
大正二年に早稲田を卒業した省吾は、父林作の帰郷の命にも従わす゛、さりとて定職にも就かず東京を離れなかった。『世間への触角』より紹介する。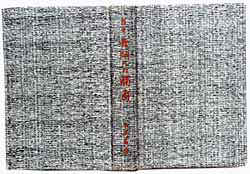
<大正二年の九月、ちょうど早稲田を卒業した私はどこか閑静な素人下宿に宿をきめて勉強しようとそちこちを探し回った。何日かを探しあぐんだ四日の昼頃である。氷川下町から西北にかけていったいに林が多く、丘陵めいたところに静かな好ましい家があるような気がされた。今は住宅地となったが、広々とした森や池があって、無数の五位鷺や鴨の巣である伊達屋敷なども近くにあって、その頃はむろん電車も開通されていなかったし、なまなか郊外よりも閑寂な落ちつきを見せていたように思われた。千川という小さい溝のような流れを北に渡ると坂になってもう丸山町である。左側はどこかの屋敷らしく、深い林で右側だけに家が並んでいる。その家の背後も林である。市内でもこんな林が残されているのかと不思議に思われるほどであった。残暑がまだひどくて、法師蝉が、オーシーツクツクとそちこちに頻りに啼いていた。以下略>
結局、省吾は下宿が見つからなかったようである。そして、『詩歌』(第3巻第10号短歌号・「白日社」発行)に散文詩「埴輪2篇」を、「詩と生命の表現」を「読売新聞」に、「詩と象徴に就いて」を「現代詩文」に、『詩歌』(第3巻第12号・「白日社」発行)に散文詩「赤児が生まれた」をたて続けに発表し、掲載されている。物書きとして生活していく決意を固めつつあった。
* 引用図書・詩集『北斗の花環』(昭和四十年七月十五日・世界文庫発行)
* 引用図書・翻訳詩集「ホイットマン詩集」(昭和二十四年三月五日・大泉書店発行)
* 引用図書・『詩に徹する道』(大正十年十二月十二日・新潮社発行)
* 引用図書・「白鳥省吾論・世界の一人を中心に」(乙骨明夫著・『國語と國文学』昭和四十四年一月号)
* 引用図書・『日本詩人』第六巻第六号(大正十五年六月一日・新潮社発行)
* 参考図書・『私の詩論大全』岩成達也著(平成七年六月一日・思朝社発行)
* 引用図書・随筆『世間への触角』(昭和十一年六月五日・東宛書房発行)
* 写真は翻訳詩集「ホイットマン詩集」・『詩に徹する道』・随筆『世間への触角』
以上・駿馬
第1回編集会議がもたれたのが、平成11年1月16日(土)でした。編集委員の皆様のおかげを持ちまして、この度ようやく出版の運びとなりました。発行日は当初、「白鳥省吾生誕110周年記念日」にしたいと思っておりましたが、少し早くなりました。編集委員の皆様のご意見を尊重しまして、1月10日に致しました。詳しいことはここをクリックして下さい。
無断転載、引用は固くお断りいたします。
Copyright c 1999.2.1 [白鳥省吾を研究する会]. All rights reserved
最終更新日: 2002/06/10