

* 縦書きのものをそのままhtmlファイルに変換しています
文責 駿馬
三. 早稲田大学入学前後
(三). 詩壇への一歩
明治四十三年(1910)、省吾二十歳。恋した少女の嫁入りに絶望した省吾に残されたものは、詩人として名声を上げ、故郷に錦を飾ることであった。それにはいっぱしの詩人としての詩を書いて見返してやるという思いがあったものと思われる。
この当時、省吾等の先生は片上伸(天弦)であった。片上天弦は明治四十年に「詩歌の根本疑」(『早稲田文学』明治四十年六月号)を発表して、岩野泡鳴の「自然主義的表象論」(『帝国文学』明治四十年四月号)とともに、自由詩運動に先鞭をつけていた。(「大正初期詩壇漫談一」より)
省吾は後に、『新しい詩の国へ』の中で「詩歌の根本疑」について、「片上天弦の論は、新しき詩風の勃興につれて当然興るべき疑問であって、要は複雑にして変化極まりなき心の波動を、どうしてきまり切った形式に盛ることが出来るかといふことであった。」と評し、同様のことを『現代詩の研究』の中では、「要は複雑にして変化極まりなき詩歌の内容と、その形式の制約拘束との矛盾に対する根本疑である。」と論じてその全文を載せている。また「自然主義的表象論」については『現代詩の研究』の中で、以下のように評している。
<岩野泡鳴の詩論は組織的には十分ではなく、独断もあったが、つねに一面の真と情熱とで、新興の青年を動かすことが多かった。ことに「自然主義的表象論」(帝国文学四月)は詩壇を刺激するところ大きかった。其れにはこれから発展すべき詩風を八箇條に挙げている。即ち、一.宗教的形式の脱却、二.懐疑と煩悶、三.神経と自然との燃焼流化、四.刹那的性欲の発見、五.心熱、六.新法語と新用語、七.思想と技巧との純化、八.新リズムである。これは泡鳴の在来の詩風の解釈と今後の希望であったが、その頃の作「わがゆらぎ」、「春晩」等を見てもわかる通り、形式上では在来の定律詩以内のものであった。>
明治四十年六月に河井酔茗は『文庫』(明治二十八年八月創刊、明治四十三年八月四十巻十二号で終刊、『少年園』『少年文庫』『文庫』と改題)より独立して「詩草社」を興し、雑誌『詩人』を発行していた。同人に川路柳虹、服部嘉香等がいた。この『詩人』九月号に川路柳虹が口語自由詩「塵溜」以下数篇の詩を発表して、詩壇に新風を巻き起こしたのであった。この時の新進詩人達の驚きの様子は、伊藤整の『日本文壇史十四』に描かれている。
今日、文学史上で口語自由詩の第一号の詩と評価されているのは、この『詩人』(明治四十年九月)に発表された川路柳虹の「塵溜」である。
塵 塚
<隣の家の米倉の裏手に/臭い塵溜が蒸されたにほひ、/塵溜のうちにはこもる/いろいろの芥の臭み、/梅雨の夕を流れて漂って/空はかつかと爛れている 以下略>(『新しい詩の国へ』大正十五年十二月二十五日・一誠社発行より転載)
この詩は『路傍の花』(明治四十三年九月)に収録する際に「塵塚」と改題されている。「現代詩に関する第一の功労者として吾人は川路柳虹を没却することができない。中略・口語による詩をはじめて作りだしたのも彼であった。以下略」とは金子光晴が『現代詩講座・詩の鑑賞3』(昭和二十五年六月三十日・創元社発行)に於いて述べている言葉である。また、同誌において小野十三郎は「然し、明治四十九年の九月の『詩人』誌上に、彼の塵塚という詩が掲載されるや、ひきつづいて口語脈による自由詩がたくさん書かれだして、それが新體詩風の定型律にとって代わって、詩壇の支配的傾向となるにいたったのである。」と 書いている。
書いている。
こうして新しい詩の時代は到来したのであった。即ち象徴詩運動と口語自由詩運動が現代の詩の基礎を築いたといえよう。『新體詩鈔』以来の欧米の詩の移入が実を結んだのである。川路柳虹はつづいて同誌にに多くの口語詩を発表したのであった。その口語詩の試作に伴って、それに賛成する服部嘉香の「言文一致の詩」(明治四十年十月『詩人』第五号)と島村抱月の「現代の詩」(明治四十年十一月『詩人』第六号)の二評論が発表された。省吾は後の『現代史の研究』に両評論を転載し、比較して後者の方を高く評価している。『新しい詩の国へ』では「現代の詩」について以下のように評している。
<島村抱月の評論は、口語の自由詩に対して幾多の問題を含む暗示に富むものであった。先ず第一に現在の詩壇の詩が直接性に欠けていることを指摘した。第二には詩と散文との境界撤廃是認し、第三にはクラッシズムの破壊を叫び、現代の言葉で書きえるものとし、ホイットマン等の自由詩をその例として挙げているのは、簡にして要を得た卓見であった。>
明治四十一年に入ると「早稲田詩社」の相馬御風は『早稲田文学』二月号に「自ら欺ける詩界」、三月号に「詩界の根本的革新」、四月号に「自殺か短縮か無意味」と立てつづけに詩の革新論を展開したのであった。その彼の主張するところは、第一に「詩の用語を日常語にすべきこと」、第二に「詩調の破壊」、第三に「行と連との自由」であった。(「自ら欺ける世界」「詩界の根本的革新」は『現代詩の研究』に転載されている)省吾はこうした詩の革新運動の波を真正面からうけ止めていた。
これら早稲田出身の詩人達によって発行された『自然と印象』の母胎、「自由詩社」の文学精神は「早稲田詩社の自然主義的、現実主義的思想の延長であった。詩の題材は人生の暗黒面をさけるものであってはいけないし、表現形式や用語は自由でリアリスティクで平易で直接的でなければならないというのが、この結社の主張であった。」つづいて、「要するに早稲田詩社も詩草社も明治初年以来の旧式な文語体定型律詩の持つ非現実的な思想と実感の失われた詩型詩語を破壊したかったのである。これを破壊し、日常使われている平易な解りやすい言葉で、口語体で自由律で現実的な素材を扱って、新しい近代詩を創造したかったのである。>(『国文学』木下常太郎著・「近代詩の結社と詩人の生態」・昭和四十年六月号・「学燈社発行)というものであった。
そして明治四十三年、詩壇の新主流は白秋、露風等の象徴詩風にあったが、愈盛んになる口語自由詩の試みは、省吾に新鮮な感じを与えていた、と同時にこれからの詩の方向を示唆していた。省吾の最も身近にあって、この傾向を持っていたのが「自由詩社」の人々であった。前述。省吾はこの新しい詩の方向にひかれて、同年二月十七日、目白台の雑貨店(「大正初期詩壇漫談一」には薬種屋とある。雑貨店は「白鳥省吾年譜」によるものであるが、恐らくは薬も扱っている店であったろうと推測する。)二階の加藤介春を訪ねたのであった。この時のことは「大正初期詩壇漫談一」に詳しいので以下にそれを抜粋してあげる。
<その頃、小石川区豊川町に住んでた片上伸氏が私達の先生だったので、訪ねたとき席上に加藤介春氏が居た、中略・それを伝としてでもあったか、私は三篇の詩を書いて片上氏の近くの薬種屋の二階借りしてた介春氏を訪ねて批評してもらった。介春氏は、静かに黙読した上に私の希望もきいてくれた、「自然と印象」の仲間にはいりたいなら紹介しよう、この詩は「自然と印象の」××君などよりよほどうまいとも褒めてくれた。人見君と私さえ承知ならいいというようなことを言ってくれたので、私は嬉しかった。
「自然と印象」の同人費は二円ぐらいとのことであった。もっともその頃の下宿料は早稲田あたりでは一ヶ月八円及至十円であった。しかし、私がその仲間にはいることに心極めしてから、間もなく、「自然と印象」は出なくなり、(全体で十集に足りなかったろう。)戯曲と詩とを中心とした「劇と詩」が秋田雨雀、人見東明の両氏の提携から明治四十三年十月に生まれるに至った。「自然と印象」の人々は殆ど全部それに加わることになった。中略・「劇と詩」の創刊号は白い表紙に舞台面の写真版の載っている気品のある菊版で、内容も戯曲と詩を主として高雅な感じであった。
私は早速その編集権発行人となっている秋田雨雀氏を鬼子母神の境内に訪ねた、中略・「詩の方は人見君が担当しているから」とのことで、人見氏を訪ねた、中略・人見氏は奥さんを亡くした頃で、小さい平家に婆やさんと寂しい生活をしていた。私の詩を見て「劇と詩」に載せることを快諾してくれた。同誌十二号に「夜の遊歩」という詩が載った。>
以上より省吾が投書家から一歩を進めて、詩人として歩みはじめる経過がおおむね分かると思う。因みに「夜の遊歩」は『憧憬の丘』詩集に収められている。
夜の遊歩
吐息しつつも字をえがくイルミネーション、
うす青き銀ふくむ夜よの凝視。
ほやけたる都会の黒と燃ゆる金とのハーモニー
鋪石に・・・・・精の黄ばんだ柳が散る。
建て続く洋館に充ち飾る種々のもの
ぱっと明るいあらゆるものに心もともに燃焼す
軽い不安の眼のよろこび。
複雑なイリュージョンにそそらるる心もち・・・・・、
ああその奥に、なにかしら寂しい遠くに。
『自然と印象』が廃刊になったのは、人見東明の「酒場」が風俗壊乱に問われ、発売禁止とされたためであった。この時期北原白秋の『屋上庭園』も同様の扱いを受け、廃刊になっている(『明治大正詩選全』より)。この年の暮れ、「無政府主義」を唱えた所謂大逆事件の判決が大詰めに近づいていた。ロシアの革命を森鴎外に調べさせた枢密院議長山県有朋は、この革命思想を国家の危機を招くとして、無政府主義、社会主義に対する取り締まりが益々厳しくなってきていた。(文芸文庫『日本文壇史十七・転換点に立つ』・伊藤整著・平成九年八月十日・講談社発行より)
* 写真上は『北斗の花環』扉裏、上は『明治大正詩選全』
* 引用図書・写真『新しい詩の国へ』(大正十五年十二月二十五日・一誠社発行)
* 引用図書・「大正初期詩壇漫談一」(『現代詩の見方と鑑賞の仕方』昭和十年九月十日・「東宛書房発行」に掲載・初出は『詩神』昭和二年三月)
* 引用参考図書・『日本文壇史十四』(伊藤整著・昭和四十七年一月二十八日・講談社発行)
* 参考図書・文芸文庫『日本文壇史十七・転換点に立つ』(伊藤整著・平成九年八月十日・講談社発行)
* 参考図書・『明治大正詩選全』(大正十四年二月十三日・白鳥省吾、川路柳虹、福田正夫編集・詩話会編・新潮社発行)
前述のように省吾は『スバル』ではなくして『自然と印象』(明治四十二年五月創刊・同四十三年六月廃刊・全十一集)を選んだのであるが、当時の文芸思潮として自然主義運動が最高潮に達した時期でもあり、また『早稲田文学』をはじめ、文壇の主要な発表機関も自然主義文学者の主宰するものがほとんどで、わずかに『帝国文学』(明治二十八年一月・上田万年、高山樗牛等創刊)系の評論家とか、森鴎外系の『スバル』、結社「パンの会」(明治四十一年十二月・太田正雄、石井柏亭等の立案になる芸術家たちの新しい交際機関)等が反自然主義的であったことからしても、当然の成り行きでもあった。(『日本文壇史十四』)以下に省吾が歌壇の人々ととつき合うことになった発端を紹介する。
師片上天弦から、「複雑にして変化無限なる所謂主観の反応感が如何にして一定の形式の中に収められ、而して其の感味の表現に遺憾なきを得るか、この問題は須く将来の詩人の自ら解決すべきものである。」(「詩歌の根本疑」より)と、今後の詩の問題点を聞かされ、自分も口語自由詩を試みたりしていた。しかし、詩の発表の場もなく悶々の日々を送っていた。そんな時に加藤介春と出会ったのであった、渡りに船と介春宅を訪ねたとしても不思議ではないと思われる。そして翌月の明治四十三年三月一日に、省吾は尾上柴舟門下の若山牧水を、早稲田鶴巻町八雲館に訪ねている。(「白鳥省吾年譜」より)その時の模様を、後年『文人今昔』に書いているので、抜粋して紹介する。
<若山牧水は酒と櫻と富士を愛し、旅を愛した歌人である。彼がまだ独身時代、早稲田の八雲館という下宿屋にいて、私が早稲田の学生時代にたずねたのが初対面である。半ば雨戸をあけた部屋に飲みかけた一升瓶が置いてあり、菓子器にかき餅のあったのは印象的であった。>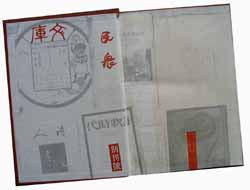
そのころ牧水は第二歌集『独り歌える』(一月一日(八少女会発行)を名古屋市の「八少女会」から発行したばかりであった。続いて新雑誌『創作』(第一期・明治四十三年三月創刊・若山牧水編集)を前田夕暮、北原白秋、三木露風等の協力を得て準備中であった。そして翌四月に創刊号を出している。(『若山牧水研究』別離校異編・森脇一夫著・昭和四十四年四月・桜楓社発行)。省吾は前年より友人の小杉寛君に連れられて、牧水の師にあたる尾上柴舟を紹介され、和歌も創作していた。この会に於いて『創作』の話を誰かから聞いて、自分の作品を載せてもらえるように、或いは、仲間に加えてもらえるように、お願いに行ったのかも知れない。
尾上柴舟は自分の教え子や、担当する雑誌『新声』の歌覧の投稿者の中から、有力な新人を選んで明治三十八年に「車前草社」を創ったのであった。このグループには正富汪洋、前田夕暮、若山牧水、三木露風、有本芳水がいた。翌三十九年、前田夕暮は脱会して「白日社」を作り、さらに四十年一月詩歌雑誌『向日葵』ヒグルマ(明治四十年一月創刊・四十二年二月二号で廃刊)を創刊し、「車前草社」の仲間はそちらに移った。その時に内藤鋠策が新たに加わった。その結果「車前草社」は自然解消してしまっていた。
前田夕暮は「白日社」を興した頃から、『スバル』(明治四十二年一月創刊・大正二年十二月終刊・全六十冊)を意識していた。それは『明星』対『新声』の延長線上のものと思われる。即ち『明星』の後身の『スバル』(反自然主義系統)対『新声』の後身『創作』(自然主義系統)、という図式から来ていると思われる。この両者にまたがって活躍したのが北原白秋である。以下に抜粋して紹介する。
<明治四十二年の一月から、その平出修が出資して、廃刊になった『明星』に代わって『スバル』が刊行されていた。これは森鴎外が中心となり、木下杢太郎、北原白秋、石川啄木、吉井勇などが有力な同人であった。>(文芸文庫『日本文壇史十六・大逆事件前後』・伊藤整著・平成九年六月十日・講談社発行)
<『創作』はその創刊号に「所謂スバル派の歌を評す、」という項目を設けて『スバル』に対抗していたが、その『スバル』の中心をなす北原白秋がここに詩と歌とを発表しているのは、やや奇異な感があった。しかし白秋は、卒業はしなかったが早稲田大学に学んでおり、しかも若山牧水、土岐哀果、佐藤緑葉等とは同級生であった。その上、若山牧水とは二度にわたって同宿の生活をし、特に親しい間柄であった。>(文芸文庫『日本文壇史十七・転換点に立つ』・伊藤整著・平成九年八月十日・講談社発行)
この『創作』は好評であった。その裏には以下のような事情があった、つづいて紹介する。
<この雑誌の創刊と時を同じくして出た前田夕暮の歌集「収穫」につづいて、若山牧水の第三歌集「別離」が翌四月に同じ東雲堂から出た。「別離」は第一歌集「海の声」と名古屋の「八乙女」発行所から前年に出た第二歌集の「独り歌える」とを合わせて、それに多少の新作を加えたものであった。この「別離」が出ると、それは「収穫」と並んで歌壇の最も人気のある歌集となった。前に出した二冊の歌集は内容が同じでありながら全く問題にされることなく、この第三歌集にいたって、評判が高くなったというのは、奇妙なことであった。それはあたかも「創作」という有力な発表機関を支配する力を持ったことが牧水の歌の評価を高めたかのようなものであった。>(文芸文庫『日本文壇史十七・転換点に立つ』・伊藤整著・平成九年八月十日・講談社発行)
七月号には伊藤左千夫、石川啄木、土岐哀果、茅野蕭々、茅野雅子、太田水穂、尾上柴舟、若山牧水、金子薫園、吉井勇、高村光太郎、相馬御風、正富汪洋、前田夕暮、佐佐木信綱、北原白秋、水野葉舟等々が写真入りで掲載された。『創作』創刊号に「所謂スバル派の歌を評す、」という項目を設けて『スバル』に対抗していたにも関わらず、スバル系の人々が歌を寄せている。因みに翌明治四十四年『創作』二月号には省吾も掲載されている。詩人としての一歩をふみしめた省吾は、これらの詩人、歌人達と終生つき合って行くことになるのである。
* 写真上は『北斗の花環』扉裏
* 引用図書・『文人今昔』(昭和五十三年九月三十日・新樹社発行)
* 参考図書・『日本文壇史十四』(伊藤整著・昭和四十七年一月二十八日・講談社発行)
* 参考図書・『若山牧水研究』別離校異編(森脇一夫著・昭和四十四年四月・桜楓社発行)
* 引用図書・文芸文庫『日本文壇史十六・大逆事件前後』(伊藤整著・平成九年六月十日・講談社発行)
* 引用図書・文芸文庫『日本文壇史十七・転換点に立つ』(伊藤整著・平成九年八月十日・講談社発行)
以上・駿馬
第1回編集会議がもたれたのが、平成11年1月16日(土)でした。編集委員の皆様のおかげを持ちまして、この度ようやく出版の運びとなりました。発行日は当初、「白鳥省吾生誕110周年記念日」にしたいと思っておりましたが、少し早くなりました。編集委員の皆様のご意見を尊重しまして、1月10日に致しました。詳しいことはここをクリックして下さい。
無断転載、引用は固くお断りいたします。
Copyright c 1999.2.1 [白鳥省吾を研究する会]. All rights reserved
最終更新日: 2002/06/10