|
|
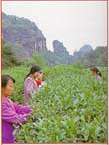
|
|
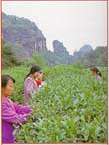
| 緑茶 | 青殺 | 揉捻 | 乾燥 | |||
| 白茶 | 萎凋 | 乾燥 | ||||
| 黄茶 | 青殺 | 初ホン | 悶黄 | 復ホン | 悶黄 | 乾燥 |
| 青茶 | 萎凋 | 揺青 | 殺青 | 揉捻 | ||
| 黒茶 | 青殺 | 渥堆 | 復揉 | 乾燥 | ||
| 紅茶 | 萎凋 | 揉捻 | 転色 | 乾燥 | ||
| 萎凋 |
茶葉をしおらせる萎凋 |
茶葉をしおらせること。野外で日にさらす「日光萎凋」と転色、風通しのよい屋内でしおらせる「室内萎凋」があります。 |
| 殺青 |
 茶葉に熱を加え酸化酵素のはたらきを止める殺青 茶葉に熱を加え酸化酵素のはたらきを止める殺青 |
茶葉に熱を加えて、発酵を止める(酸化酵素を働かないようにする)工程。 |
|
揺青 (ヤオチン) |
茶葉を軽く揺さぶること。茶葉に細かい傷をつけて発酵をゆるやかに促し、香りを引き出すための、青茶特有の工程。 | |
| 揉捻(復揉) |
|
お茶のでを良くしたり、発酵を促すために、お茶を揉む工程。二度目の揉捻のことを復捻といいます。 |
|
ホン焙 (ホンベイ)初ホン 復ホン |
熱を加えて水分を取り除きながら、葉を乾燥させていく工程。黄茶のように製造工程で二回ホン焙が行われる場合、一度目を初ホン、二度目を復ホンといいます。 | |
| 乾燥 |
低温で乾燥させる |
茶葉を乾燥させる工程。 |
|
悶黄 (メンファン) |
まだ水分が多く含んだ茶葉を高温多湿な場所に放置し、菌の働きで、軽く後発酵させること。黄茶独特の工程。 | |
|
渥堆 (ウオドゥイ) |
水分の多く含んだ茶葉を高温多湿な場所に放置し、菌の働きで発酵を起こさせる黒茶独特の工程。 | |
|
転色 (ジュアンソー) |
茶葉を充分に自家発酵させること。紅茶独特の工程です。 |
|
上の表のように、中国茶には大きく分けて6つの製造方法があります。それぞれの製法の特徴的な部分を見ていきましょう。 まず、緑茶。摘みとった茶葉をすぐに熱処理し、酸化酵素が働かないようにする、不発酵茶ならではの製法が特徴。これは「殺青」という工程で、日本茶の場は蒸す方法が一般的で、中国緑茶の場合は釜で炒る方法が取られることが多い。殺青した茶葉を揉捻、乾燥させる工程には4つの種類がありあます。 白茶の製造方法はとてもシンプルで、、萎凋した茶葉を乾燥させる段階でわずかに火入れし、酸化酵素の働きを止める方法です。 |
| 黄茶の製法の特徴は「悶黄」という工程。これは水分をまだ残した状態の茶葉を積み重ねて、高温多湿な場所に放置するもの。同じ後発酵茶の黒茶に近い製法だが、二度のホン焙と二度の悶黄を繰り返してつくられる、大変手まのかかったお茶です。 |
| 青茶の製造工程で特徴的なのは、「揺青」という工程。言葉どうりに、茶葉を揺すったり混ぜたりして茶葉の表面に細かな傷をつけ、青茶独特の芳香成分を引き出すものです。この他、茶葉によって製造方法はすこしづつ異なり、発酵度や味、香りの異なる青茶が生まれます。 |
| 黒茶は、それ自身が持つ酸化酵素の働きではなく、菌類の働きによる発酵であることが最大の特徴です。殺青、揉捻という工程の次に行われる「渥堆」では、まだ水分の残る茶葉を重ねて、高温多湿な場所に放置し、菌の力でゆっくり発酵させる。この後、復揉・乾燥が行われます。 |
| 完全発酵である紅茶は、強い揉捻を行った後に、温度と温度、通風などを調節することによって、短時間で充分な発酵させる「転色」という工程が独特です。 |
| 名月園トップへ戻る|中国茶トップへ戻る |