|
|
|
|
 |
栄西が中国から持ち帰った茶の種子を植えたという佐賀県東脊振村。 栄西から茶の種子を贈られた明恵上人(栂尾山高山寺石水院) |
|
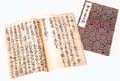 |
臨採宗を広めるために奔走する栄西の足元にはいつも茶があったという。その栄西が二日酔いに悩む将軍 源 実朝(みなもとの さねとも)に対して、一杯のお茶とともに「茶の徳を誉める所の書」をさし出した。これこそ我が国最初の茶専門書「喫茶養生記」です。 |
|
 秋に花をつけます
秋に花をつけます
|

|
茶の木の原産は中国南部またはインドのアッサム地方といわれています。「お茶を飲むこと」の起源が中国であることは間違いありませんが、いつであるかは明らかにされてはいません。古くから中国には毒を消すために茶を用いたという伝説がありますが、近世になるまでの長い間、茶が高貴な薬物とされていたのは中国のみならず世界の各地でも同様であったようです。例えばあるイギリス人の1660年9月28日の日記には「今日はじめて茶を喫す、妻は風および下痢の良薬と聞きたる茶なる飲料を煎出せり」と書かれています。 |
| わが国では仏教の伝来とともに中国から茶の栽培と製造法や喫茶法が伝わりましたが、茶は禅僧が眠気を除くため、また上流貴族社会の社交の道具として用いられただけで、一般大衆の物とはならないまま随分長い期間を経て、北条・足利時代に漸く「茶の湯」となって発達し、豊臣時代に有名な千利休らによって「茶の湯」の形式が完成されるにしたがって武士から一般庶民の間に次第に茶は行き渡りました。このように茶は千年以上もの長い間にわたって日本人の生活・文化に大きな影響を与えましたが、茶が産業として発展するようになったのは、安政6年(1859年)に横浜が開港されて、その年に180トンが輸出されたことに始まるといってよいでしょう。そして、明治時代には茶が生糸とともにわが国貿易品の花形であり、茶が日本の全輸出額の20%〜30%を占めた時代がありました。 |